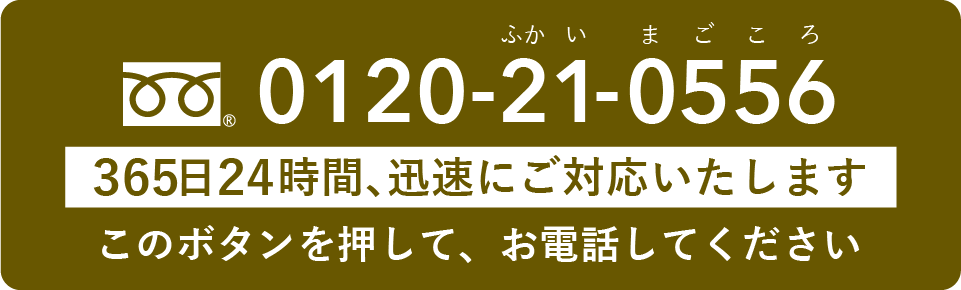2018/05/12
「あの日見た星」
夕日の持つ絵筆が水田を橙色に染めていた。そしてその向こうに直立不動の姿勢で立つ杉林が,小高い山の線を描く農村地帯で山崎定七は生まれた。短い期間に第一次世界大戦や関東大震災を経験した大正最後の年であった。
定七の家は農家だった。両親は夜明けとともに田圃に出て汗を流し、日が暮れる頃戻ってきた。働きづめに働いて六人のこどもたちを養った。
定七には四人の姉とひとりの妹がいた。やんちゃでひょうきん者の定七は農家の跡取りだったが、百姓を嫌い、逃げるようにして、故郷を捨て京都の高等蚕糸学校に駆け込んだ。
夏は蒸し風呂のように暑く、冬は冷凍庫のように寒い不親切な京都の気候に慣れた頃、定七のもとに一通の封書が届いた。封を開けずとも中は解った。召集令状だった。
学徒出陣により熊本の追撃砲隊に配属され特攻の訓練が始まった。日を追って劣化する待遇で戦況の悪化はそれとなく定七にも察知できた。
毎日のこの厳しい訓練に果たしてどれほどの意味があるのか、兵舎の窓から外を眺めながらそう思った。そこには星のまたたきは届いたが希望の光は射してはいなかった。
いよいよ定七にも玉砕覚悟の特攻命令が下される時が来た。劣勢は足のくるぶしまで濡らしていたのである。定七は上官から呼び出された。そしてこう言われた。「家が農家の者は国へ還り農業に専念すべし」と。「助かった」。思わず心の中で叫んでしまった。
次の瞬間あれほど嫌っていた家業に救われたと言う渋みをもった唾が口の中に広がった。国民が陛下の玉音放送に涙したのはその二ヶ月後のことであった。
うつむき加減に戻った故郷は戦火を逃れていた。温かく迎えてくれた家族の優しさが定七の心のかさぶたに染みた。
それから定七は人が変わったように家族のために働いた。そして農作業に勤しむ一方で勉学にも励んだ。これからは学問が身を助けると定七は確信していたのだ。
定七の読みは間違っていなかった。国は教育や経済に力を入れ始めた。そのような中、定七は戦後最初の教員試験に合格し高校の教壇に立つことになった。
戦火で親兄弟を失い、敗戦に打ちひしがれた若い命を定七は歯を食いしばりながら導き続けた。生徒たちの目が兵舎の窓から覗いた星のまたたきに見えた。希望のない闇夜に見た定七の生きる道しるべだった。「何とかこの子たちに希望の光を与えたい」。そんな心が教壇に立っていた。
振り返ると定七の教員生活も五十七年を数えていた。世の中は変わった。時代は流れていた。定七の人生も昼の盛りを過ぎ夕暮れが近づいていた。「早くしないと日が暮れてしまう」。そんな思いで定七は人生の歩みを速めた。
高校の教壇を降りると養護学校の講師を務めた。やはり定七は教育の世界から離れられなかった。さらに自分の時間も楽しんだ。休みは釣りと旅行三昧だった。そしてのめり込んだ菊作りは素人の域を超え数々の賞に輝いた。
また大阪に嫁いだ娘が連れて帰るひ孫に逢うことも定七の心を和ませてくれた。立派に育った息子や娘たち、そして六人の孫、四人のひ孫が集まり年に数度食事会が開かれた。もう故郷を捨てた青い時代や、戦火の中進むべき道を見失った彷徨の日々は古い絵巻物の中に納められ、団らんと言う灯りが皆を優しく温かく包んでいた。
「玉不磨無光」…「玉磨かざれば光無し」。あの夜希望と言う光を見失った定七の座右の銘だった。
定七の夕暮れは暗さを増してきた。そろそろ人生の帳が下りる頃になった。
その年の梅雨の訪れは早かった。初夏の日差しを遮る灰色の雲が一面を覆い、篠突く雨が木や花や土を濡らした。どこかで蛙の鳴き声が聞こえ定七が息を引き取った。一度失いかけた命は八十六を数えていた。
死後、家族が定七の机のひきだしを開けた。そこには自分で選んだ遺影の写真と息子や娘ひとりひとりに宛てた手紙がそっと納められていた。